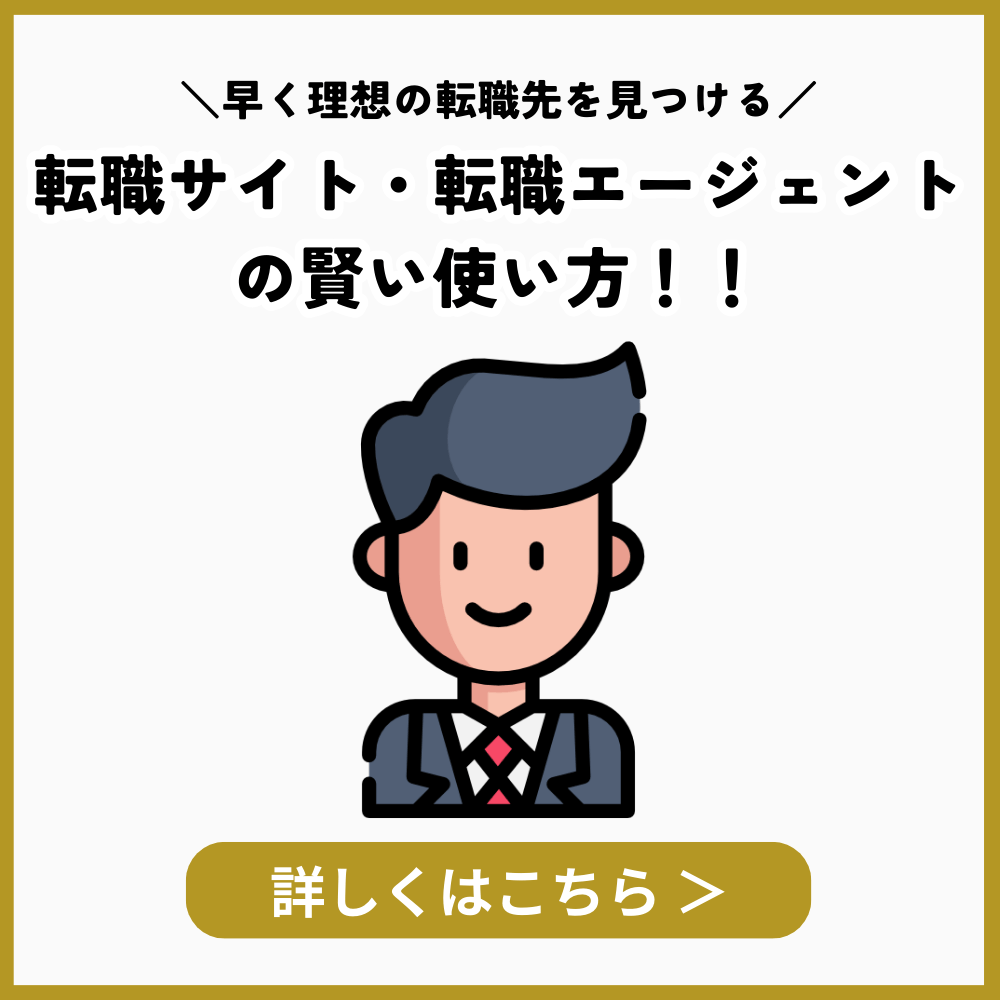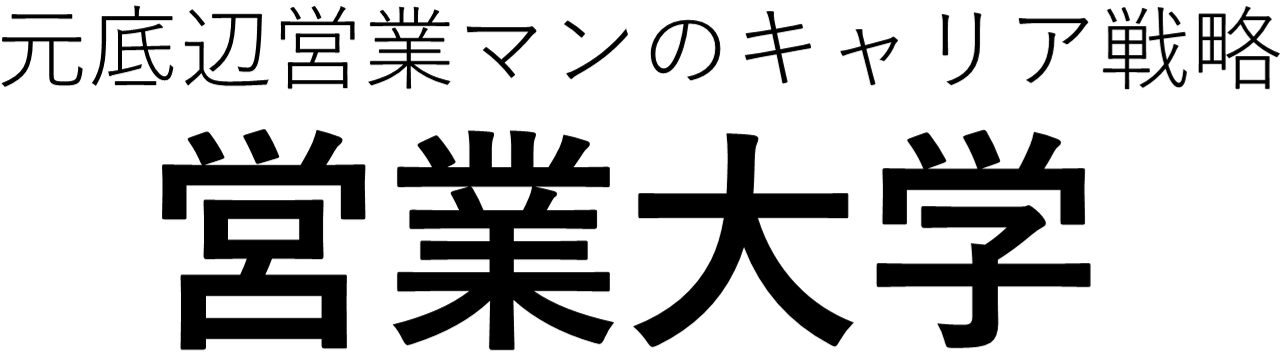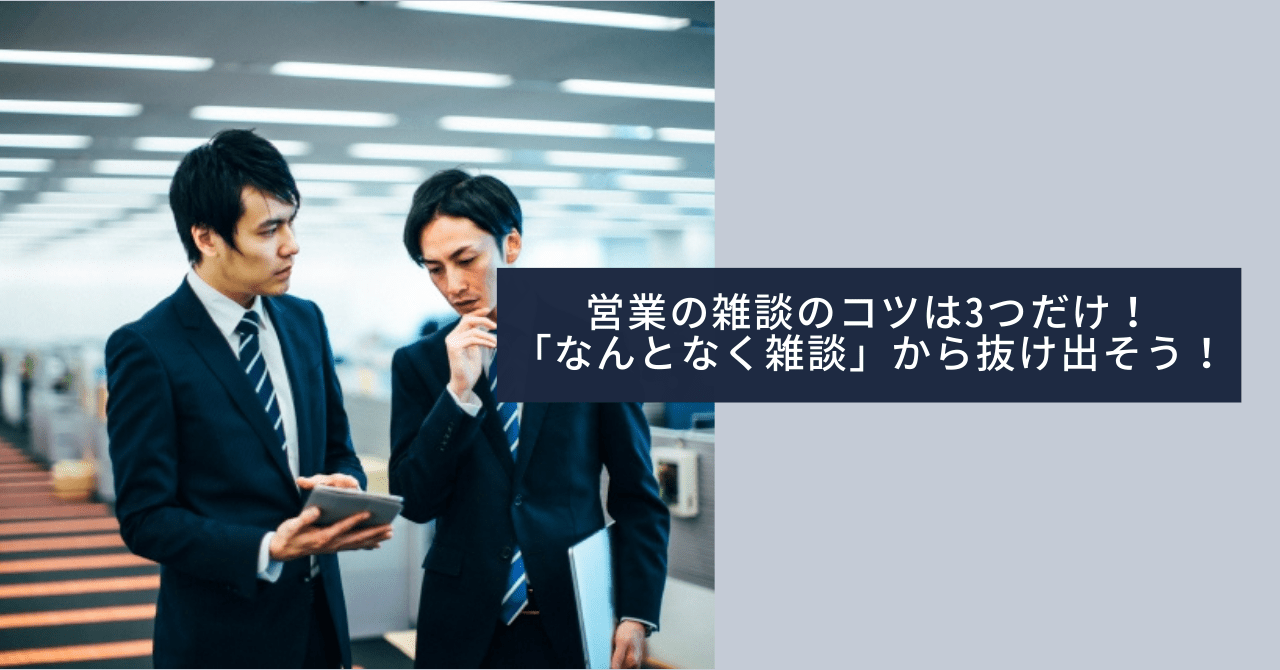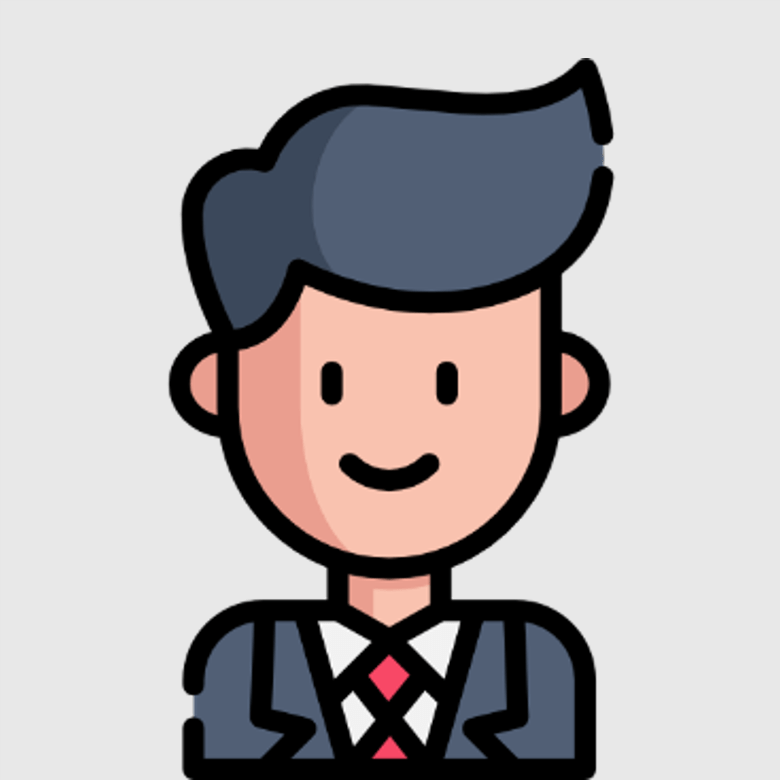- 雑談って重要なの?
- どうやって雑談すればいいの?
- とりあえず季節の話とかしておけばいい?
このような悩みを解決する記事となっています。
営業における雑談は軽視されがちで、なんとなくこなすだけの人が多いような気がします。
たとえば、「最近暑くなってきましたねー」といったような誰にでも共通するような話をすればいいといった勘違いも多く、それでは雑談のための雑談になってしまい、打合せの時間が減ってしまうだけのただの無駄な時間になってしまいます。
ここでは、営業が雑談をする重要性や雑談のコツや注意点についてご紹介します。
営業における雑談とは?
営業の種類に関わらず、営業の基本的なプロセスは以下のようになります。
- リスト選定
- ニーズの仮説構築
- アプローチ
- 商談(雑談/ヒアリング/仮提案)
- プレゼン・クロージング
- 見込み顧客管理
営業における雑談は、顧客との面談の最初のステップで行われます。
しかし、「今日天気悪いですね。」「お子さんはおいくつなんですか?」といったような、一般的な雑談をすればいいかというと営業の場合は少し違うんですよ。
営業の雑談の重要性
営業の雑談の重要性については、以下の2つがあると考えています。
- 人間的信頼関係の構築ができる
- ビジネス的信頼関係の構築への橋渡しができる
重要性1:人間的信頼関係の構築ができる
人間的信頼関係とは「人として好かれる」といった感情に関わる話のことです。
たとえば、以下のようなものです。
- 話しやすい
- あの人なら安心できる
- 全力でやりきってくれる
- 言い訳をしたりしない
- 嘘をつかない
- etc…
「あの営業は人として嫌だ」と思われてしまったら、そもそも商品やサービスを売るスタートにも立てなくなってしまいます。
なので、そのスタートに立つために、雑談をして人間的信頼関係を構築していきます。
重要性2:ビジネス的信頼関係の構築への橋渡しができる
ビジネス的信頼関係とは「仕事の質が良い」といった機能や品質に関わる話のことです。
たとえば、以下のようなものです。
- 使いやすい
- 見やすい
- わかりやすい
- 便利だ
- etc…
「あの営業は人として好きだけど仕事のクオリティがイマイチ」となってしまっては、いずれは顧客もしびれを切らしてしまいますよね。
ビジネス的信頼関係を構築していくためには、ある業界に精通していたり、自社の商品やサービスに関する圧倒的なスペシャリストになるしかありません。
ただし、このビジネス的信頼関係を構築するには、人間的信頼関係が構築されていることが前提になるので、雑談は「ビジネス的信頼関係の構築への橋渡し」となるべきなのです。
営業の雑談のコツ
営業が雑談するときのコツは以下の3つだと考えています。
細かいテクニックについては、様々な本にも書かれているとは思いますが、結局、今から紹介する3つのポイントに集約されると思っています。
- 当たり前のことを当たり前にやる
- 共通の話題を持つ
- 価値観に共感する
コツ1:当たり前のことを当たり前にやる
そもそも当たり前のことを当たり前にできなければ、人間的信頼関係を築くことは難しいです。
たとえば、打合せのアポイントに15分遅刻してきた人がいたら、「こっちも忙しい中時間空けたのに」「時間の管理があまりできない人なのかな」と思い、この会社、この人とは一緒に仕事したくないなと思っていしまいますよね。
このように「遅刻をしない」といった当たり前のことが当たり前にできないと、人間的信頼関係を築くことができません。
遅刻をしない以外にも以下のようなものがあります。(雑談以外のことも含まれます)
- 見た目を整える
- 嘘をつかない
- 挨拶をする
- 敬語を使う
- etc…
これらは一般的にできて当たり前と思われているもので、意識をすれば誰にだってできるものになるので、着実に実行していきましょう。
コツ2:共通の話題を持つ
同じ出身地である、同じ出身校である、同じ趣味を持っているといった共通項が多いほど人間的信頼関係を構築しやすくなります。
たとえば、「実は私、〇〇さんと同じ大学なんですよね!」と言われたら、親近感が湧くのと同時に「何年の卒業ですか?」「では、〇〇については覚えてますか?」といったように会話が盛り上がり、共感を感じやすくなります。
今やインターネットで検索すれば相手の興味のあるものや出身校といった情報は簡単に手に入るようになりましたので、アポイント前に相手に関する情報を集めることをおすすめします。
 元底辺営業マン
元底辺営業マン私の場合、個人のSNSなどまで深く見ると悪い印象を与えかねないので、インタビュー記事などからネタを探しをしています。
コツ3:価値観に共感する
絶対に揺るがない人間的信頼関係を構築していくためには、相手の価値観や生き様に共感していくことが必要になります。
人は「自分の話を聞いてくれる」「自分の価値観に共感してくれる」と思った相手に対して、信頼する傾向にあります。
なので、営業としては、「相手が話したいこと」を事前に調査しておき、たくさん話をしてもらえるように仕向けないといけません。
しかし、何でもかんでも「相手が話したいこと」を引き出させればよいということではなく、その話題選びが重要になってきます。
一番良いのは「経営上の悩み」「仕事上の悩み」で、この辺りの悩みは同僚にも相談しづらかったり、家族に話をしても理解を得られにくく、第三者である営業マンには話しやすく、唯一の相談相手だと思ってもらえれば、大事なパートナーというポジションを得ることができます。
営業の雑談の注意点
営業における雑談の注意点についてもお話していきます。
- 流れを意識する
- 定番のネタに頼るだけではダメ
注意点1:流れを意識する
出身校が同じということで話が盛り上がっていたのに、いきなり「お時間もなくなってしまうので、早速本題なのですが・・・」と、流れを切ってしまうと雑談の効果も薄れてしまいます。
なので、本題に遠からず近からずのところからは始まって、自然と本題に入れることが理想の流れとなります。
しかし、何も考えずに打合せに挑むと、ぎこちない流れになってしまいがちなので、事前にどんな話題から始めて、本題に入っていくのかシミュレーションしておきましょう。
たとえば、個人的な趣味からスタートする場合は、スポーツだった場合、チームをまとめる難しさの話をして、そこから会社経営の話にもっていくなど、いくつかパターンを持っておけば楽になります。
また、ビジネス寄りの話から始める場合でも、あらかじめパターンを作っておいて、そこに当てはめるように会話できれば毎度考える必要はなくなります。
- 従業員数:育成方針→研修プログラムの確認→自社研修サービスの紹介
- 業績:過去の成長率→新規顧客と既存顧客の割合→既存顧客育成のためのCRMの紹介
注意点2:定番のネタに頼るだけではダメ
ここまで読み進めてきたあなたは、もうお分かりだと思いますが、なんでもかんでも定番ネタを使えば良いというわけではありません。
雑談において、有名なものに「木戸に立てかけし衣食住(きどにたてかけしいしょくじゅう)」というものがあります。
- 木:気候や季節の話
- 戸:道楽(趣味)の話
- に:ニュースの話
- 立:旅の話
- て:天気の話
- か:家族の話
- け:健康の話
- し:仕事の話
- 衣:ファッションの話
- 食:食べ物の話
- 住:住まいの話
営業においては、これらの中から適当に選択して、なんとなく雑談すれば良いということではないですが、そのような人が多いのも事実です。
これらは雑談ネタの参考にはなりますが、上のコツで見たように「共通の話題を持つ」「価値観に共感する」を意識したネタ選びをしなければなりません。
まとめ
本記事では、営業が雑談(アイスブレイク)をする重要性や雑談のコツや注意点について紹介しました。



営業のコツをまとめて知りたい方は、是非以下の記事もお読みください。