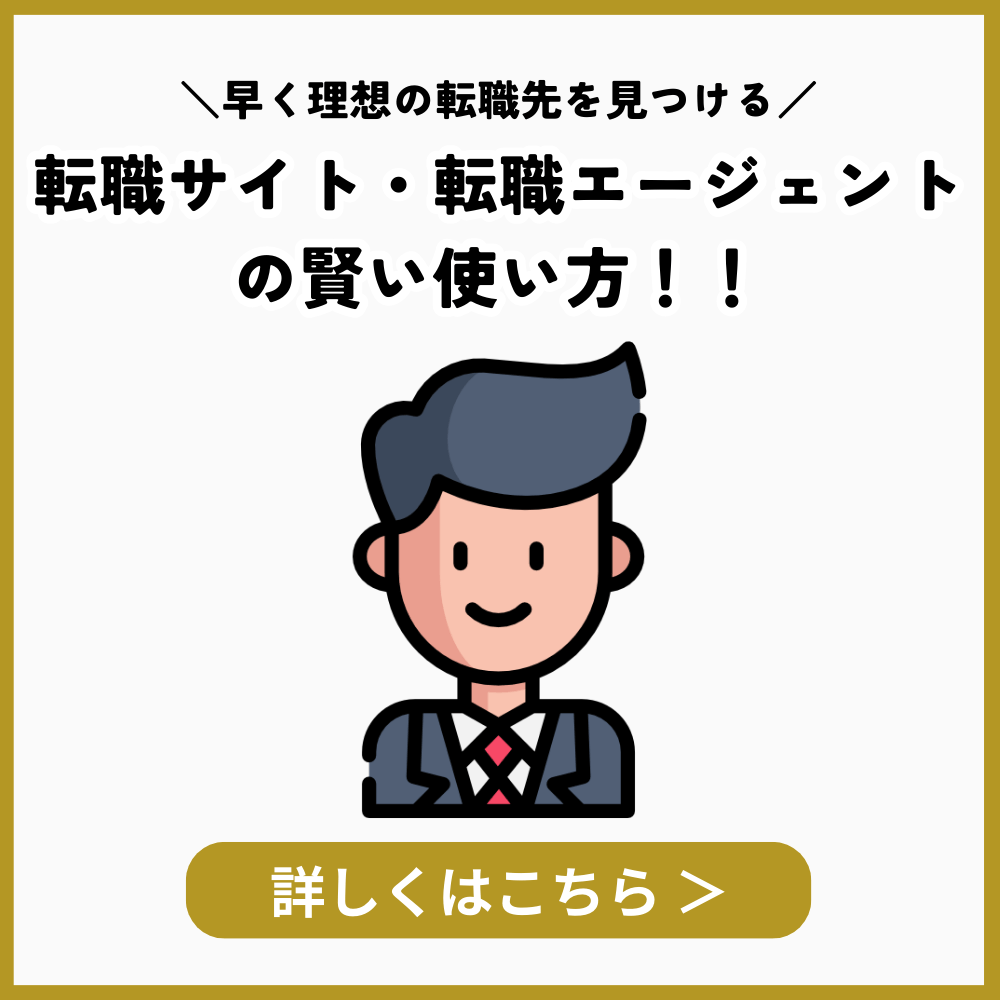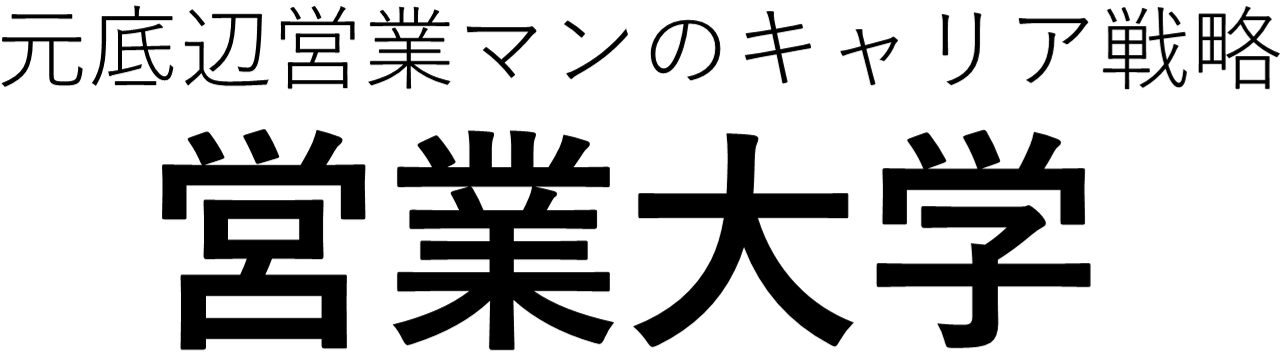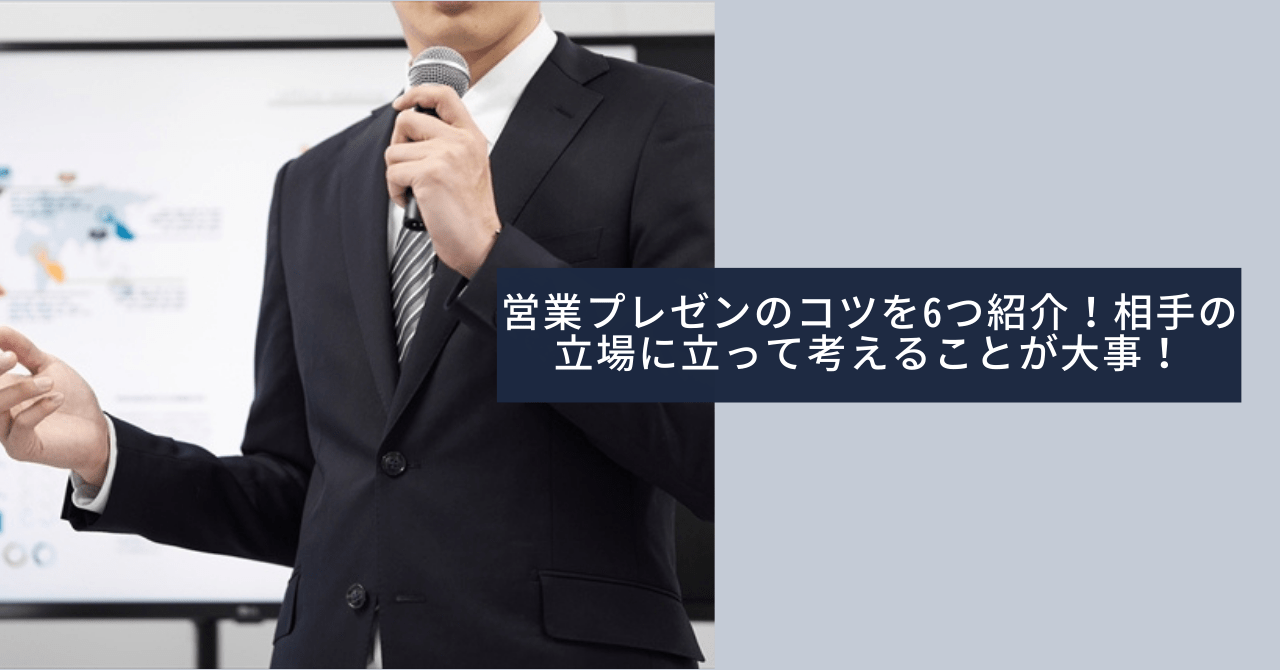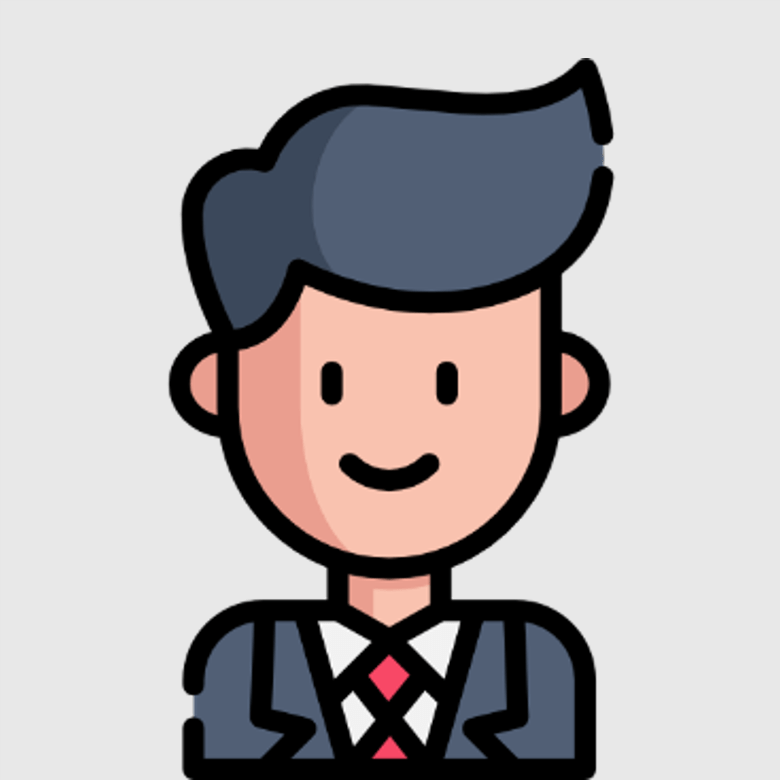- プレゼンで上手く話せない。
- どうやってプレゼンすればいいかわからない。
- プレゼンの通過率がなぜか悪い。
このような悩みを解決する記事となっています。
プレゼンと聞くと「いかに上手く伝えるか」に重きを置いてしまう人がいますが、それは大きな間違いです。
そういったこちら側の視点で考えるのではなく、プレゼンをした相手側の視点に立って「どうプレゼンしたら購入してもらえるか」といったように考えなければならなりません。
このこちら側から相手側に視点を変えるといったことを意識するだけでもプレゼンは大きく変わっていきます。
ここでは、営業プレゼンの前・中・後に分けて、それぞれのコツについてご紹介します。
営業におけるプレゼンとは?
営業の種類に関わらず、営業の基本的なプロセスは以下のようになります。
- リスト選定
- ニーズの仮説構築
- アプローチ
- 商談(雑談/ヒアリング/仮提案)
- プレゼン・クロージング
- 見込み顧客管理
この営業のプロセスを見て頂くと、顧客に対していきなり「当社の〇〇という商品はおすすめです!」と提案するのは違うことが分かりますね。
リスト選定によって、買ってくれそうな顧客を選定して、ニーズの仮説構築によって、どのようなニーズを抱えてそうかあたりをつけ、顧客へのアプローチをして、面談をして、初めてプレゼン(提案)をしなければなりません。
また、プレゼンは「上手く伝えるプレゼン」ではなく「顧客の課題を解決するプレゼン」でなければならないのです。
「顧客に提案してと言われたからプレゼンする」「顧客の課題が明確ではないけど運よく採用されればいいからプレゼンする」といったことは、プレゼンにかかる時間や労力を考えると避けたいところです。
 元底辺営業マン
元底辺営業マンたまに「プレゼン数」をKPIしているといったことを聞きますが、プレゼン数が増えると成約数が増えるとは限らないということですね。
営業プレゼンのコツ(事前準備編)
まずは、営業プレゼンの事前準備のコツについてご紹介します。
- プレゼンのゴールを意識する
- プレゼンの構成を押さえる
- プレゼンは決裁者にする
事前準備1:プレゼンのゴールを意識する
冒頭お伝えした通り、プレゼンは「顧客の課題を解決するプレゼン」になりますので、準備したものを上手く話すことをゴールに設定してはいけません。
ゴールは以下の2つを意識することが大事なのです。
- 相手がプレゼン内容を社内に説明できる
- 相手がプレゼン内容を社内に説明したいと思う
相手が直接の決裁者でなければ、その人がプレゼン内容を理解して、社内に説明できなければ商談はそれより先には進めませんので、理解してもらえるように丁寧に説明していきましょう。
また、そもそも「社内に説明したいくらい良いプレゼンだ!」と思ってもらえなければ、社内の関係者にこのプレゼン内容は届きませんので、論理的な説明に加えて、感情にも訴えかけなければいけません。



相手が社内に上手く説明できなさそうであれば、その場に立ち会って説明するということも必要です。
事前準備2:プレゼンの構成を押さえる
基本的なプレゼンの構成(=プレゼンの資料の構成、話す順序)については、最初に「なぜ必要か」といった課題を解決する必要性を示して、次に「何をすべきか」といった解決策を示し、最後に「具体的にどうするか」といった実行策を示していきます。
- なぜ必要か(Whyの明確化):店舗運営をしている顧客は販売機会のロスや廃棄ロスが常態化しているため、売上の伸び悩み、コスト増に繋がっており(=課題)、ここをテコ入れすることが必要
- 何をすべきか(Whatの明確化):前月の売れ行きを参考にして、次月の店舗・商品毎の売れ行きを予測する
- 具体的にどうするか(How・When・Whereの明確化):毎月の店舗・商品毎の売れ行きを可視化できるツールを導入する
このようにプレゼンは課題ありきになりますので、課題が明確になっていないのであれば、プレゼンをするべきではありません。



とにかく自社のサービスを紹介すれば、受注数のUPに繋がるという考え方は間違いですね。
事前準備3:プレゼンは決裁者にする
先ほどのコツ1で「相手がプレゼン内容を社内に説明できる」をゴールとすべきと言いましたが、理想はもちろん決裁者に直接プレゼンすることになります。
なので、ヒアリングの段階で決裁者が誰なのかを引き出す必要がありますし、決裁者にプレゼンしたいことを伝えなければなりません。
しかし、普通に「決裁者に会わせてください」と言っても、相手が「この営業マンを決裁者に会わせる価値がない」と判断されてしまえば、会わせてもらえません。
その前にしっかりと相手と信頼関係を築いて、「この営業マンの話はためになりそうだから決裁者に会わせてみるか」と思ってもらう必要があります。
営業プレゼンのコツ(実践編)
先ほどの事前準備が終わったら、次に実際にプレゼンに入っていきます。
- ストーリーテリングを活用する
- 顧客と対等で話す
ポイント1:ストーリーテリングを活用する
ストーリーテリングとは、コトバンクでは以下のように定義されています。
出典:コトバンク
- 「ストーリーテリング」とは、伝えたい思いやコンセプトを、それを想起させる印象的な体験談やエピソードなどの“物語”を引用することによって、聞き手に強く印象付ける手法のことです。
なぜ、このストーリーテリングが重要かと言うと、人は何かを判断するときに「論理」と「感情」といった両面を持って判断しているからです。
なので、プレゼンが論理的な説明であったとしても、感情を動かせなければ商品やサービスの購入を促すことができないので、感情面を動かすことができるストーリーテリングを活用していきます。
- ストーリーテリング:私はかつてダメ営業マンだったんです。でも逆にダメ営業マンから這い上がったからこそ、みなさんの悩みを把握しており、その悩みを解決する具体的な方法がわかるんです。
- 論理的な説明:営業が身に付けるべきスキルは3つあり、1つ目は論理的思考力、2つ目は・・・」
そして、具体的なストーリーテリングのやり方は、「顧客のありたい姿と現状とのギャップ=課題」がどのように解決されるのかをストーリーで説明していくのです。



「当社の商品をこのように使っていくことによって、目指している姿を達成することができるんです!」と。
ポイント2:顧客と対等で話す
「当社に支援させていただきたい」や「我々はその分野におけるリーディングカンパニーです」といった営業トークはNGということです。
このような営業トークをしてしまうと、相手側は「時間をとって話をわざわざ聞いてあげている」「購入してあげる」といったように立場は上だと勘違いされてしまいます。
そもそもプレゼンは顧客の課題解決策を提供しているのであって、別に押し売りをしているのではないので、顧客側から「ぜひ、その解決策を教えてください!」と言われるくらいの存在になり、こちら側が主導権を握るくらいのスタンスでなければなりません。
そのためには、こちら側が主語ではなく、顧客側を主語にすれば良いです。
具体的には「当社に」「我々は」といったこちら側を主語にするのではなく、「御社はこの商品を使うことで、こんな未来が待っている」「このような解決策であなたは悩みを解消できます」のように「御社は」「あなたは」といった顧客側を主語にすればいいんです。
このように主語を変えることによって、顧客側に「我々のために考えてくれている」が伝わり、課題解決パートナーという地位を獲得することができるでしょう。
営業プレゼンのコツ(事後編)
最後に、営業プレゼンが終わった後のコツについてご紹介します。
- 検討期間を区切る
フォロー1:検討期間を区切る
「検討させてください」と言われて、「はい、わかりました」と言い、そのまま2,3週間連絡が来なかったという経験はあるのではないでしょうか。
「検討させてください」と言われた場合は、必ず期限を区切るようにしなければいけないんですよ。
それはなぜかと言うと、時間が経てば経つほど気持ちが冷めていき、1週間以上経ってしまうと提案の半分も覚えてないといった状態になってしまうからなんですね。
とはいえ、「今決めてください」「明日までには回答をください」はあまりにも失礼になってしまいます。
なので、1週間くらいを目途に返事をもらうようにして、プレゼンに希少価値を持たせておけば、相手の良い判断を引き出せる可能性が高まるんですね。



大手企業になると2週間に1回稟議を通す会議があるといったこともあるので、その場合は仕方ありませんが、その会議の日時を把握しておいて、確認するようにしましょう。
まとめ
本記事では、営業プレゼンのコツをプレゼン前・中・後に分けて紹介しました。



営業のコツをまとめて知りたい方は、是非以下の記事もお読みください。