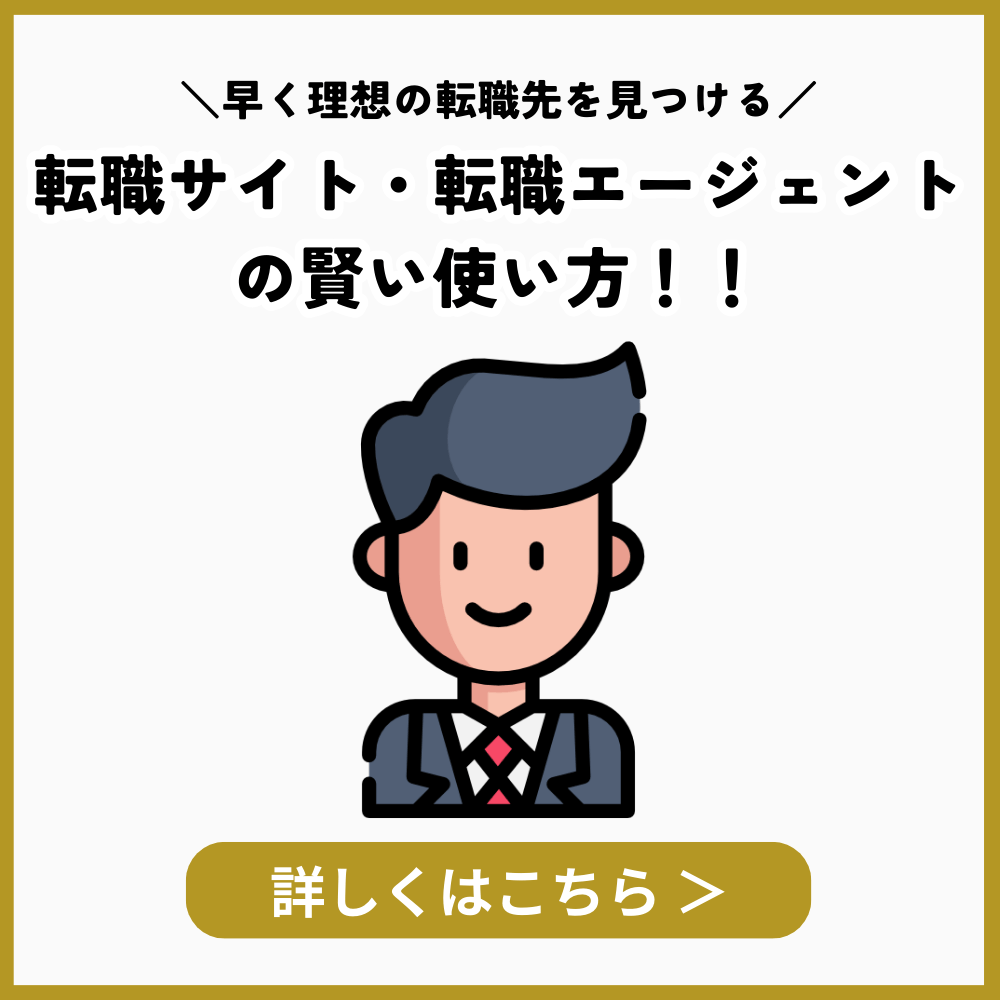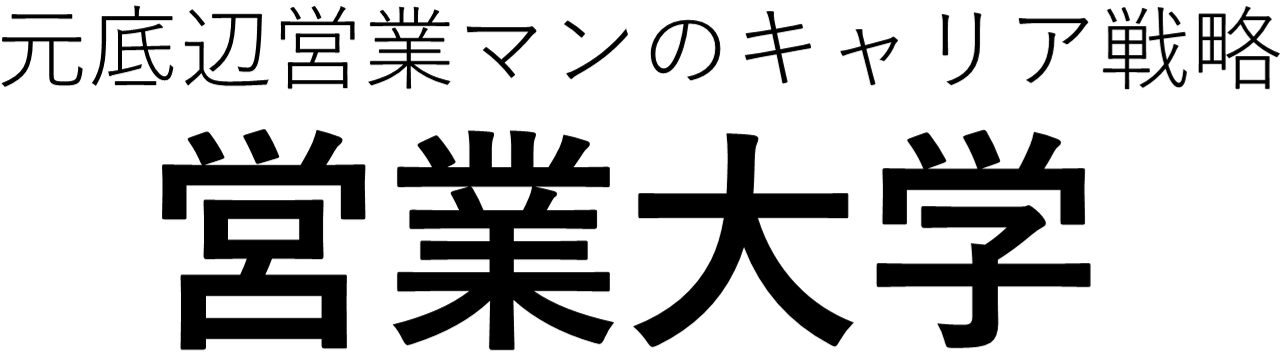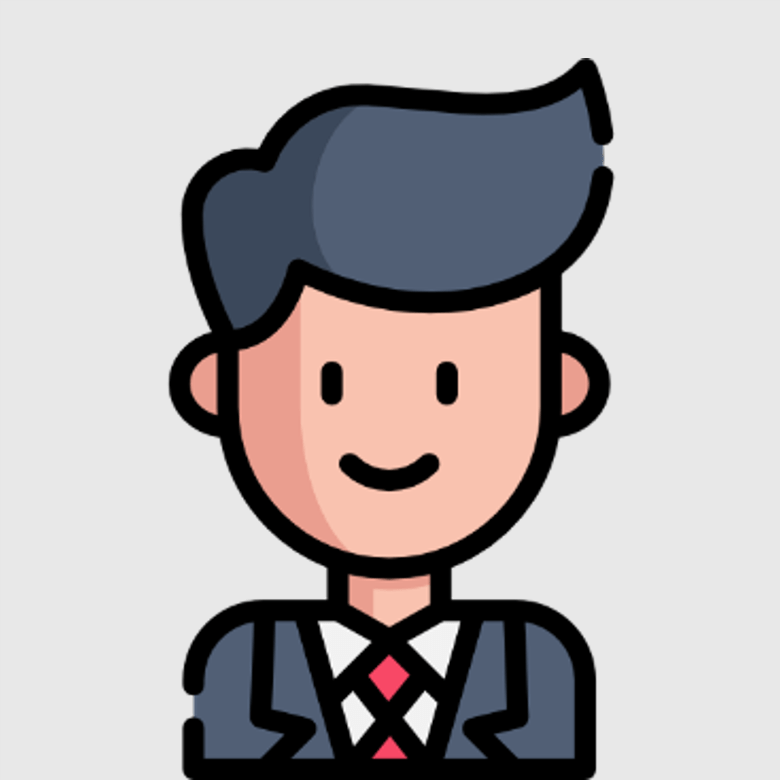ー 営業のヒアリングに関する記事一覧 ー
- 現状、目標、課題、解決策
- 納期
- 予算
- キーマン
- 購買プロセス
- 評価基準
- 競合他社
- キーマンってそもそも誰?
- 「キーマンを押さえろ」とか言うけど、そんなに重要なの?
- 良い提案をしているのになぜか受注できない!
「いつも商談の詰めの段階で詰め切れずに終わってしまう」といった悩みがある場合、キーマンがしっかりと押さえられていないということが原因かもしれません。
「いや、いつも偉い人には会えているから問題ない」と思っていたら、それは少し違います。
キーマン=偉い人ではなく、実はキーマンにはいくつかのタイプがあって、それぞれをしっかりと押さえてないといけません。
そうすれば、商談の詰めで詰め切れなかったという事態を避けることができます。
ここでは、キーマンを押さえる重要性、押さえ方、アプローチの仕方についてご紹介します。
営業がキーマンを押さえる重要性
営業は「キーマンを押さえろ!」と言われますが、それは「どんでん返しが起きないようにするため」です。
特に法人営業では、商品やサービスが高額になってくると担当者の一存で購入を決断することができず、関係部署に問題がないかチェックをしてもらったり、役職者から決裁をもらったりする必要が出てきます。
たとえば、情報システム部門から引き合いがあって、毎日の店舗毎商品毎の売上が色々な指標で見れる可視化ツールを提案する場合を考えてみます。
- 情報システム部門にヒアリングをしてみると、情報システム部門としては日々の売上を管理しているデータベースからデータを吸い上げて、可視化ツールと連携できるのかといった技術的な視点でクリアできるのかといったことを気にしており、実際に可視化ツールを使うのは営業部門とのことでした。
- そして、営業部門の本部長にヒアリングをしてみると、可視化ツールの目的は、日々の店舗毎商品毎の売上から来月の売上を予測して、商品の仕入れを最適化したいとのことで、これが実現できるのであれば購入は営業本部長が決めるとのことでしたが、購入条件やコストに関しては総務部が関係してくるとのことでした。
このように見てみると、情報システム部門に対しては、技術視点で問題ないことを伝える、営業部門の本部長に対しては、実現可能性や効果を伝える、総務部に対しては、コストの条件をクリアしていることを伝えなければならないのがわかります。
したがって、商談に関わる人達(キーマン)を把握していれば、あとになって「コストが合わなくてダメでした」「技術的問題がクリアできる提案をしてなかったので不採用になりました」といった「どんでん返し」が避けられます。
 元底辺営業マン
元底辺営業マン担当者からはOKが出ていて、契約成立間近になったかと思いきや、結局ダメだったという経験はありませんか?
営業が押さえるべきキーマンのタイプ
先ほどのように、法人営業かつ高額商材になるほど、商談に関わる人達が多くなるので、「誰に、どのタイミングで、どのようなアプローチをするか」といったことを考えなければなりません。
商談では主に以下の3つのタイプの人が存在し、それぞれに適切にアプローチすることが重要です。
- キーパーソン(決裁者)
- チェッカー
- ユーザー
タイプ1:キーパーソン(決裁者)
キーパーソンは、商談において鍵となる人物のことで、予算面で最終的な判断をする組織の中で業績に責任を負っている人になります。
この人がGOと言えば、誰がなんと言おうとGOになり、中小企業であれば社長がキーパーソンであることが多いです。
大手企業になると金額にもよりますが、部長職以上の管理職がキーパーソンになるケースがほとんどです。
キーパーソンの気にするポイントとしては「儲かるのか」「コスト削減できるのか」ということになり、経営目標を達成するために必要なものかどうかを最終判断していくことになります。



案件に対して一番影響力のある人物です。
タイプ2:チェッカー
チェッカーは、提案内容に対してアドバイスをする人で、内容に問題がないかを見つけます。
技術的な視点で仕様やスペックが条件を満たしているのか、法務的な視点で契約条件を満たしているのかなどをチェックしていきます。
直接購入をGOとする権限はないのですが、NOと発言することはできますので、チェッカーによって商談が進まないことがあります。
実際はチェッカーがキーパーソンの役割を一部担っている場合がありますので、しっかりと押さえておくことが重要となります。
タイプ3:ユーザー
ユーザーとは、提案された商品やサービスを実際に使う人になります。
ユーザーは商談の初期に現れる場合もあれば、納品をする段階に現れる場合もあります。
商談の初期の段階では、ユーザー側からこんな不満を持っているという話を持ち掛けられ、現状の意見や要望を述べることもあれば、納品をする段階で「このシステムを導入することは決まっているのは知っているけど、使いやすさを考えて少し手を加えてくれ」といったこともあります。
使いやすさ、便利さなどについて、ユーザーの意見を参考にすることがほとんどです。
ユーザーは人数としてはかなり多くなりますが、その中でも上からの信頼が厚い人が発言権を持ち、商談のGO、NOGOにも少なからず影響してきます。



キーパーソンは、現場のユーザーが使いこなせなかったり、反対されたりする解決策を導入しても成果が上がらないことを知っています。
営業が押さえるべきキーマンのニーズ
法人の場合、商品やサービスの購入は組織で決断をするわけですが、実際に商談で相手にするのは個々の人間です。
人によって興味・関心が異なるため、組織のニーズに加えて、個人のニーズも押さえなければなりません。
- 組織ニーズ
- 個人ニーズ
ニーズ1:組織ニーズ
組織ニーズとは、その組織においての役割やミッションに沿ったニーズになります。
キーパーソン、チェッカー、ユーザーの組織ニーズには、それぞれ以下のようなものがあります。
キーパーソンの組織ニーズ
キーパーソンの組織ニーズは、以下のようなものがあります。
- 財務のニーズ:売上・利益、コスト、生産性
- 競争のニーズ:シェア、競合との差別化、ブランド力
- イメージのニーズ:離職率、リスク回避
キーパーソンは経営的な判断を求められる立場です。
彼らは経営指標などの数字で評価がされるので、正直、数字にしか興味がありません。
そのため、商品やサービスの機能が良いといった定性的なものよりも、購入することで売上が〇円UPするといった定量的なメリットを伝えていくことが重要なのです。



キーパーソンは「結局、いくら儲かるの?」が口癖です。
チェッカーの組織ニーズ
チェッカーの組織ニーズは、以下のようなものがあります。
- 技術のニーズ:品質、耐久性、実績など
- ルールのニーズ:価格、取引条件、法との整合性
チェッカーはミスのない判断や評価をすることが求められる立場です。
そのため、専門的な知見から提案された内容に問題がないか確認をしていきます。



チェッカーは「本当に大丈夫?」が口癖です。
ユーザーの組織ニーズ
ユーザーの組織ニーズは、以下のようなものがあります。
- 業務のニーズ:使い勝手、作業効率
ユーザーは商品やサービスを使って成果を出すことが求められる立場です。
そのため、自分達の業務が上手くいくのか、業務効率化のための機能や性能を備えているのか、といった点を興味があります。



ユーザーは「使いやすいの?」が口癖です。
ニーズ2:個人ニーズ
個人ニーズとは、その個人特有の価値観等に由来するニーズになります。
組織ニーズは最低限押さえるべきもの(=いわゆる建前)ではありますが、実際には人は建前だけで動く生き物ではありません。
たとえば、新しいもの好きの人であれば、従来のものより「いかに最新の技術が採り入れられているか」を重視するでしょうし、慎重派の人であれば、新しいものより「いかに安全性が担保されるか」を重視するため、それぞれの人に合わせて提案の仕方も変えなければいけないということです。
そして、その個人ニーズについては、以下のようなものがあります。
- リスク回避、安全性
- 新しいものへの興味
- 周囲から受け入れられるか
- 評価、昇進



個人ニーズは、商談の中での発言やインタビュー記事等から垣間見ることができます。
営業がキーマンへアプローチするステップ
キーマンには、キーパーソン、チェッカー、ユーザーの3つのタイプがあると言いましたが、この中でも最も重要なのがキーパーソンです。
担当者に提案が受け入れられなかったとしても、キーパーソンに提案をしたら受け入れられたといったことは普通にあったりします。
キーパーソンは最も商品やサービスの効果に興味があるので、「費用対効果が高いから予算オーバーでもやるべきだ!」「前例がないけど競合他社に差をつけるためにやるべきだ!」と言って、進めてくれることがあります。
なので、ここでは主にキーパーソンへのアプローチのステップについてお話していきます。
- キーパーソンの探し方を考える
- キーパーソンへ話す内容を考える
- キーパーソンへ近づく
ステップ1:キーパーソンの探し方を考える
キーパーソンは役職や組織図から推測する方法があります。
過去に同じような規模の会社で同様の取引をした際に、どの役職者が決裁者であったかを基に推測したり、組織図からアプローチ先の決裁者を推測するという方法もあります。
また、以下の質問をストレートにぶつけてみるという方法もあります。
- 決裁の仕組みはどうなっているのか
- Aさんが最終決裁権を持っているという認識でよいか
- 他に最終決定権に影響を与える人はいるのか
だいたいこの質問を投げれば把握できるのですが、特に最後の質問は重要となります。
というのも、キーパーソンは承認をするだけで、実は技術に詳しい人の意見を大いに加味して、最終決定をしている場合があるからです。
この場合は、キーパーソンだけでなく、技術に詳しい人までしっかりと押さえなくてはなりません。



ホームページからキーパーソンを探ったり、訪問したときの受付の電話横によくある座席表から探るのもありです。
ステップ2:キーパーソンへ話す内容を考える
先ほども言いましたが、キーパーソンは経営的な判断を求められる立場です。
売上が上がる、コストが下がる、生産性が上がる、競合に勝てるといったことにしか興味がありません。
なので、どうしたらそれらが実現可能になるのかといった情報であったり、どれくらい効果があるのかを具体的な数字で示していくことでより興味を持ってもらえるようになります。



商品やサービスの機能やスペック等の話は興味ありません。
ステップ3:キーパーソンへ近づく
一つ目は、担当者からキーパーソンを引っ張り出してもらう方法です。
担当者に商品やサービスを良いと思ってもらえたり、担当者の権限やリスクの範囲を超える判断が必要な場合は、担当者はキーパーソンを巻き込まざる得ません。
また、解決策を検討している段階では、キーパーソンの意思決定や意向によって、解決策の方向性や金額が大きく変わることを伝えることでキーパーソンを引き出す方法もあります。
二つ目は、キーパーソンに直接メール、電話、手紙などでアプローチする方法です。
ただし、担当者からすると「勝手にうちの上司にアプローチしやがって」と思われてしまう可能性がありますので、担当者へは事前にアプローチして良いかということは確認しておきましょう。
さらに三つ目は、社内の他の人からアプローチしてもらう方法です。
担当者は「一営業担当者をキーパーソンに会わせるわけにはいかない」と思っていることがありますので、キーパーソンと同等の役職者からアプローチしてもらったり、社内に話そうとしている専門家がいれば「最新の情報を提供する」等と言って、キーパーソンの同席を促すこともできます。
まとめ
この記事では、営業がキーマンを押さえるのコツについて紹介しました。
ー 営業のヒアリングに関する記事一覧 ー
- 現状、目標、課題、解決策
- 納期
- 予算
- キーマン
- 購買プロセス
- 評価基準
- 競合他社



営業のヒアリングをまとめて知りたい方は、是非以下の記事もお読みください。