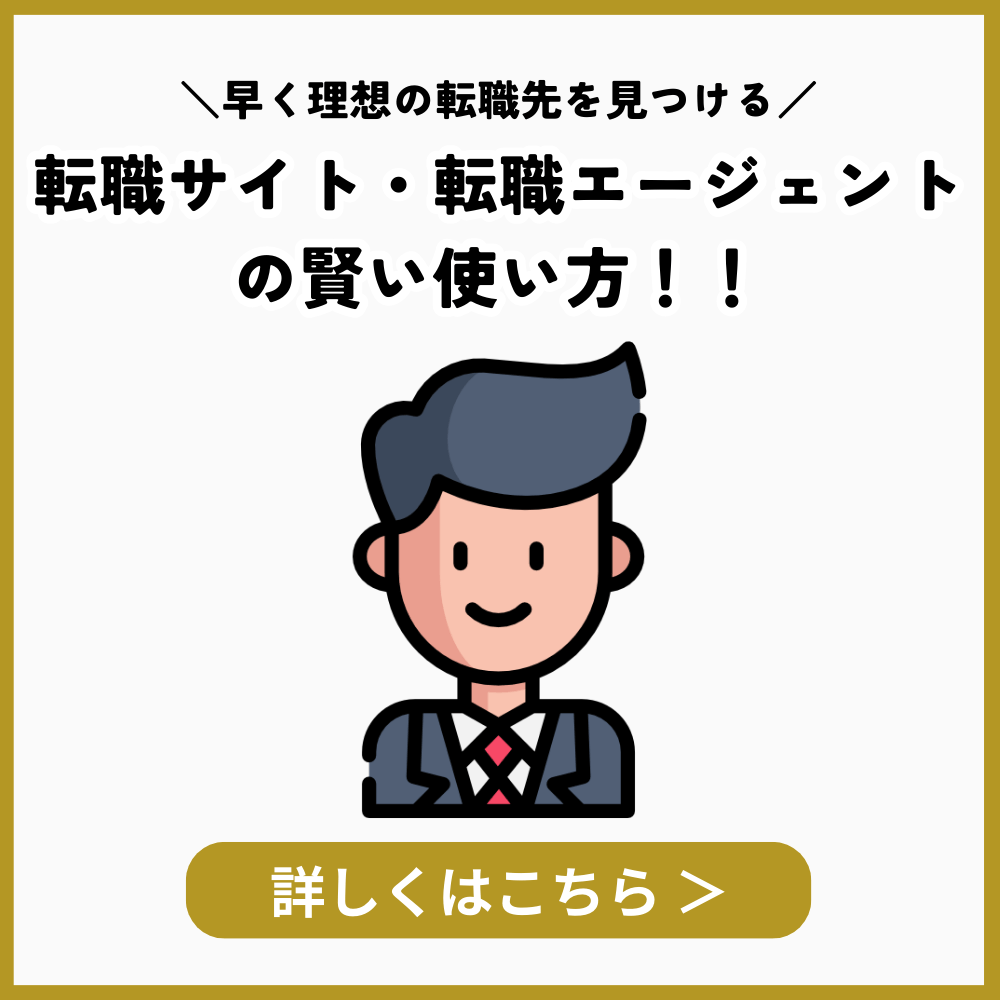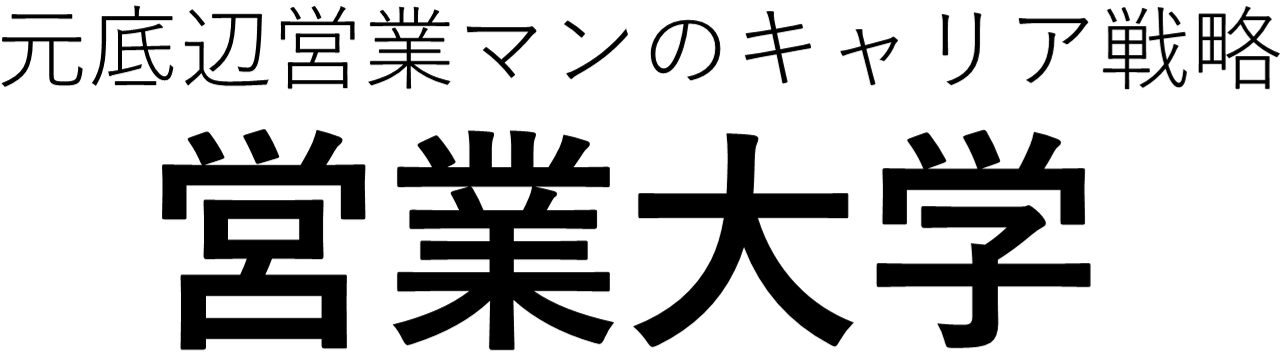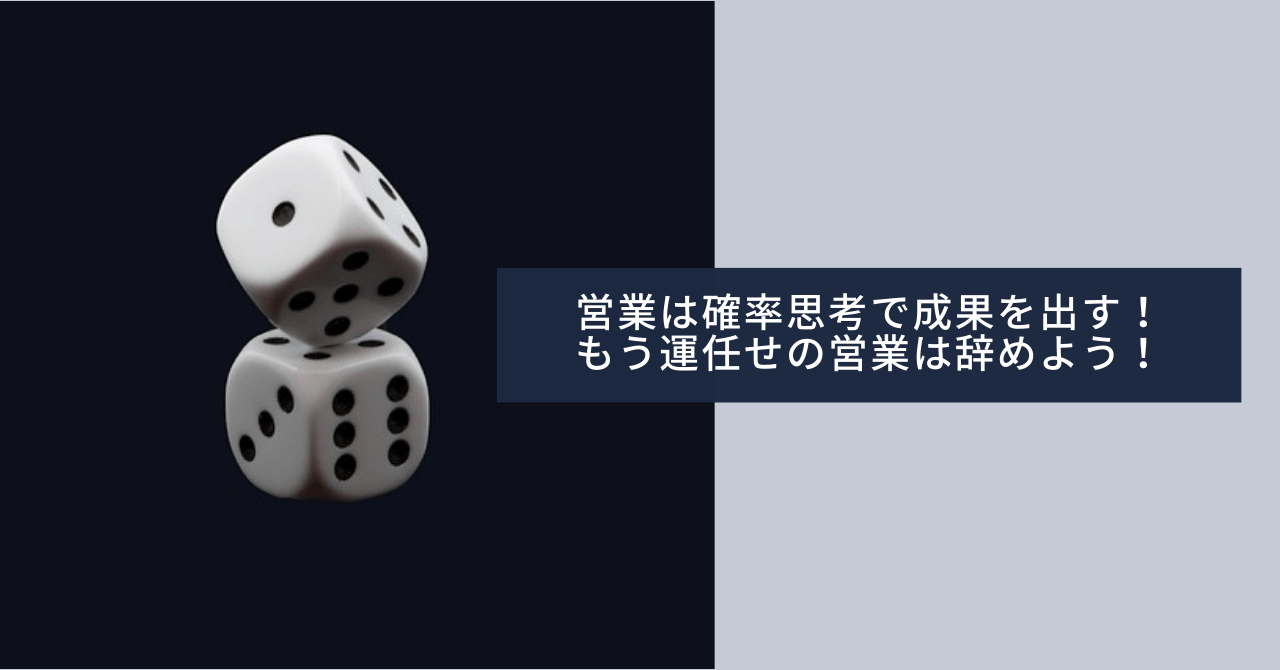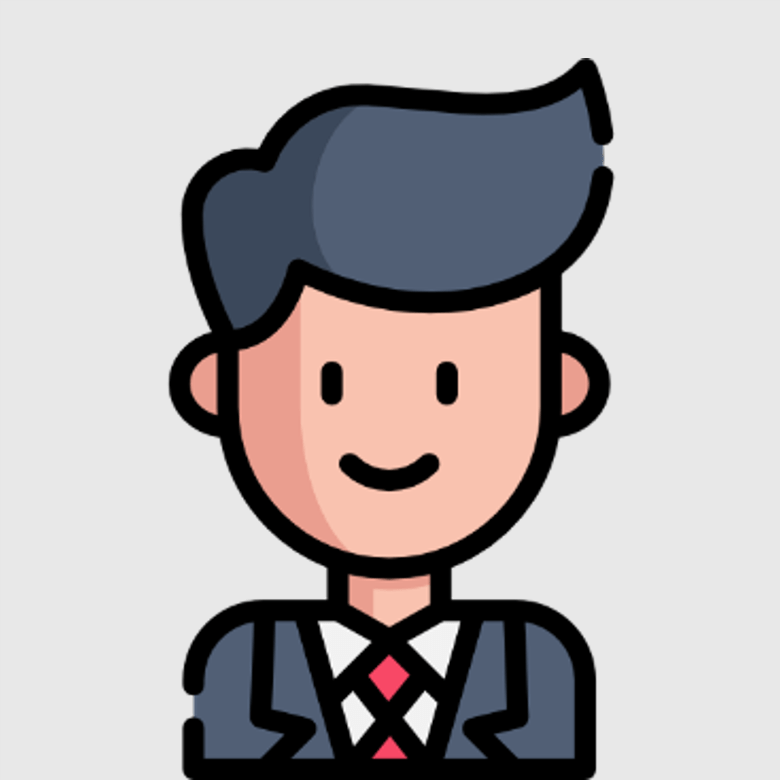- 断られまくって辛い!
- 売上目標にいつも到達しない!
- 目標に対して結局どれくらい行動すればいいの?
このような悩みを解決する記事となっています。
「営業は確率思考」と聞くと「ギャンブルじゃないんだから!」と思うかもしれません。
しかし、この確率思考を理解をすると、目標を達成するためにするべき行動が明らかになります。
ここでは、営業に必要なスキルの一つである「確率思考力」のメリットややり方についてご紹介します。
確率思考とは?
まず、そもそも確率思考とは何なのかを見てみましょう。
その名の通り「確率で物事を考えること」になります。
- このアイスは10%の確率で当たりが出るから、当たり5つの景品をもらうためには、50個は買わないと・・・
- バスケのシュート成功率20%しかないから、せめて50%くらいにならないとレギュラーになれないな・・・
上記はあくまで例ですが、このように日常生活においても、確率で物事を考えている場面はあると思います。
 元底辺営業マン
元底辺営業マン今回はそんな単純なお話です。
営業が確率思考をするメリット
では、なぜ営業にとってこの確率思考が重要なのでしょうか。
それは以下の3つのメリットがあると考えているからです。
- 売上目標を達成するための行動が明確になる
- 自分の課題を抽出できて改善に繋げられる
- 精神的に楽になる
メリット1:売上目標を達成するための行動が明確になる
経験上、営業マンでちゃんとした行動計画を作っている人は少ないです。
あなたもなんとなく日々営業活動していて、「目標に近いのか、遠いのか」「今のペースで目標に届くのか否か」といったことを把握してないのではないでしょうか。
このように、行動計画を作らなければ、たまたま目標を達成することもあれば、大幅に目標を下回ってしまうことがあったりと、目標達成が運任せになってしまいます。
一方で、確率思考で考えることで、たとえば簡単な例で言うと、過去の経験から「契約確率は3%程度」といったデータがあれば、「目標が契約3件獲得だから見込み客へ100件程度アプローチしよう!」といったように行動計画が立てられます。



こうすることで、運任せの営業から脱することができるのです。
メリット2:自分の課題を抽出できて改善に繋げられる
「売上目標を達成できた or 達成できなかった」という事実を把握しているだけでは、今後の成長は見込めません。
成長をしていくためには、「なぜ売上目標を達成できなかったのか」といったように、課題を抽出していかなければなりません。
たとえば、「テレアポの成功率は10%だけど、その次のクロージングの成功率が1%だから、1000人にテレアポをしてようやく1件の成約が取れる状況か・・・」と把握していたとします。
そうすると、「これだとどれだけ時間があっても売上目標に届かないから、成約率を上げるコツを先輩に聞いてみよう!」と具体的な行動が移せるのです。
このように確率思考を使うことで、自分の営業活動のどこに課題があるのか把握でき、今後の成長へと繋げられるということです。
メリット3:精神的に楽になる
営業は「埋もれた宝を発掘する」ようなもので、100件の顧客にアプローチして、契約に至るのはせいぜい2~3件(=契約確率は2~3%)ということはざらにあったりします。
仮にそれがトップ営業マンだったとしても、5~6件の成約としかならず、誰であっても契約に至らない方が多いのが普通です。
それなのに、1件の顧客にアプローチして断られると、「自分が否定をされているような気がする」「こんなことやってられない」となってしまう人もいます。
しかし、最初から「誰であっても契約に至らない方が多い」と分かっていればどうでしょう。
たとえ断られたとしても、「よし!この顧客はリストから外せる!さあ次々!」と前向きに考えることができるようになります。
営業が確率思考をするときのステップ
次に、具体的な確率思考のやり方をご紹介します。
確率思考するときのステップは以下の2つになります。
- 営業プロセスを分解
- 各プロセスの数と次プロセス移行確率を出す
ステップ1:営業プロセスを分解
まず最初に、自分の日々行っている営業活動のプロセスを分解していきます。
一般的には、以下のように営業プロセスを分解できます。
- リスト選定
- アプローチ
- 面談
- プレゼン
- クロージング
会社によっては、リスト選定はリストが上から降ってくるだけであって、自分自身でコントロールすることができないといったものがある場合は、除外してしまいましょう。
また、商品やサービスの価格が低ければ、面談、プレゼン、クロージングの3つのプロセスを1つに集約できる場合があるので、そのときは1つにまとめてしまいます。



会社独自の営業プロセスが間に入るようであれば、それを追加していってください。
ステップ2:各プロセスの数と成功確率を出す
次に、分解した営業プロセス毎の数と成功確率を出力していきます。
まずは、過去の経験に沿って次の式に数字を埋めていきます。
- リスト選定数×リスト化成功率=アプローチ数
- アプローチ数×アプローチ成功率=面談数
- 面談数×面談成功率=プレゼン数
- プレゼン数×プレゼン成功率=クロージング数
- クロージング数×クロージング成功率=成約数
仮に前月は次のようだったとします。
- 100件×90%=90件(アプローチ数)
- 90件×30%=30件(面談数)
- 30件×50%=15件(プレゼン数)
- 15件×20%=3件(クロージング数)
- 3件×100%=3件(成約数)
このように見ていくと、だいたい1件の成約をするためには、33件のリスト選定数、30件のアプローチ、9件の面談・・・が必要だということが分かりますよね。
もし、今月の目標成約件数が5件だった場合、「約185件(≒5÷0.9÷0.3÷0.5÷0.2÷1)ほどのリスト選定数が必要になってくるが、今より85件のリスト数を増やすにはどうすればいいのか?」といったように考えることができます。
また、「クロージングの成功率が低いのは、何が原因で解決策はどうすればいいのか?」と改善に向けたネクストアクションにも移ることができます。
このように数字で見える化してしまえば、営業活動においてどこが課題になっているのか、目標に到達するにはどれだけ行動すべきかが分かりやすくなります。
営業が確率思考をするときの注意点
最後に、確率思考をするときの注意点です。
- 各プロセスの成功率UPは長期目線で考える
注意点:各プロセスの成功率UPは長期目線で考える
先ほどまでは過去の経験から成功率を出力して、それを基に行動する「量」を計画するという話をしましたが、もちろん成功率を上げることも重要です。
その各プロセスの成功率とは営業活動の「質」に関わるところです。
しかし、いきなり面談でのヒアリング力が一気に向上したり、プレゼンにおける提案力といったものが劇的に上がることは考えにくいですよね。
なので、質については長期的に改善する計画を立てていく必要があります。
このように質の向上には時間が掛かってしまうので、最初にテコ入れする箇所としては、「量」である「リスト選定数を増やす」といったような、そもそもの入口を増やす活動に着手することをおすすめします。
また、各プロセスの成功確率を上げる質に関するところでも、「リスト化率」や「アプローチ成功率」は、比較的容易に改善することができるのであれば、すぐに着手する価値はあります。
まとめ
本記事では、営業が確率思考をするメリットや確率思考のやり方について紹介しました。



営業に必要なスキルをまとめて知りたい方は、是非以下の記事もお読みください。