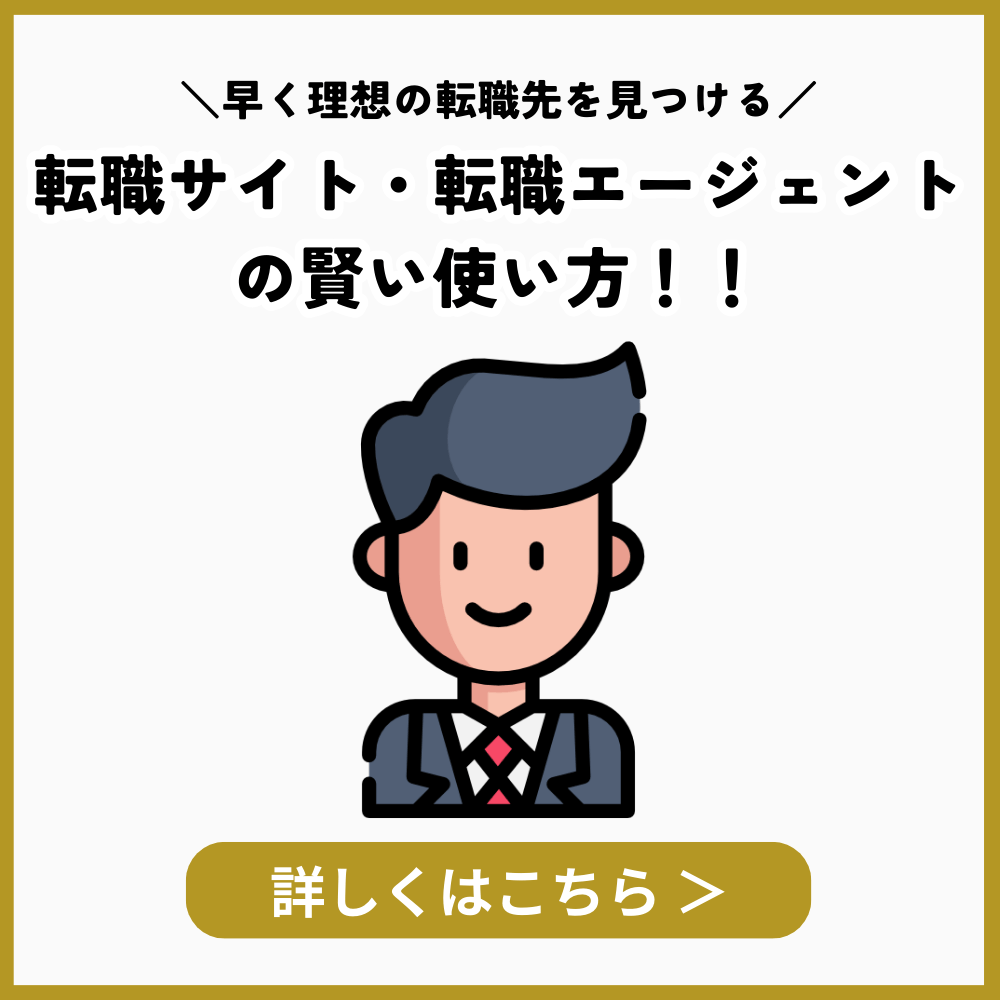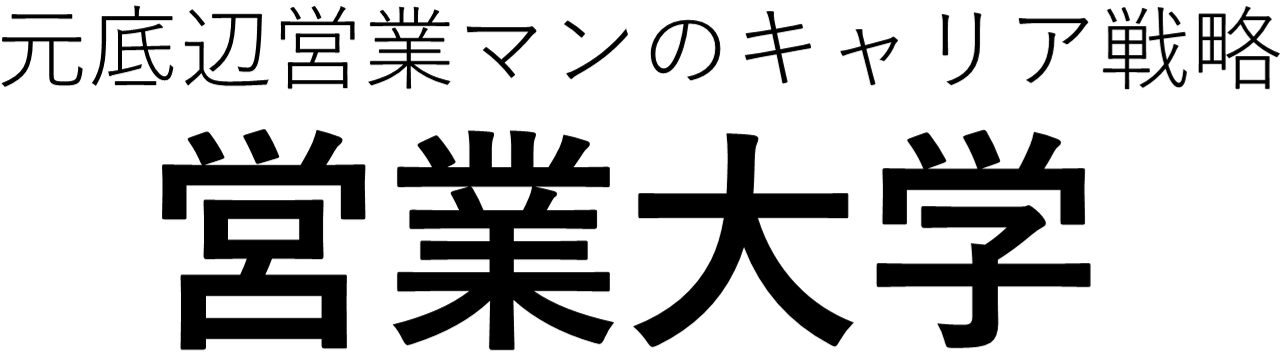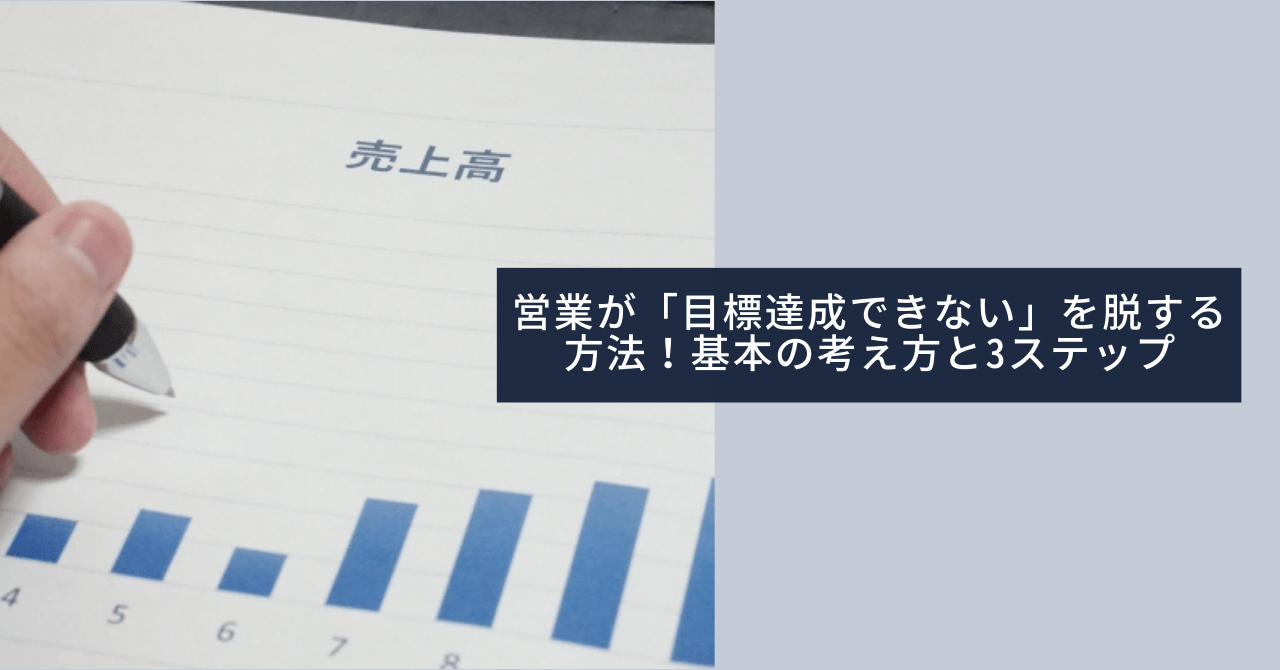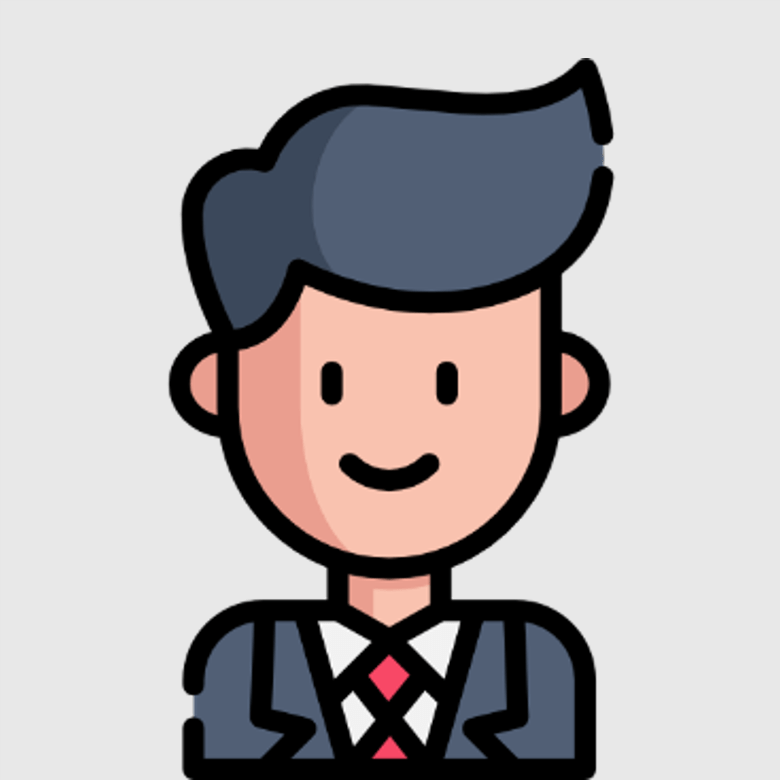- いつもなんとなく案件をこなしている。
- 安定して営業目標を達成したことがない。
- どうすれば営業目標に到達することができるの?
このような悩みを解決する記事となっています。
コンスタントに売上目標を達成できていますか?
ここでは、営業が目標を達成するための基本的な考え方や具体的なステップについてご紹介します。
営業における見込み顧客管理とは?
営業の種類に関わらず、営業の基本的なプロセスは以下のようになります。
- リスト選定
- ニーズの仮説構築
- アプローチ
- 商談(雑談/ヒアリング/仮提案)
- プレゼン・クロージング
- 見込み顧客管理
「目標を達成するときもあるし、達成しないこともある。目標を達成することもあるから営業スキルには問題がなく、たまたま案件の巡り合わせが悪いだけだ」と思っていたら大きな間違いです。
事実、いつも目標を達成する人も存在しているので、「たまたま案件の巡り合わせが悪いだけ」といった言い訳は通用しません。
実は、その「いつも目標を達成する人」になるためには、見込み顧客管理(=パイプラインマネジメント)といった考え方を採り入れていく必要があるのです。
 元底辺営業マン
元底辺営業マン見込み顧客管理のやり方については、後ほど詳しく解説します。
営業に目標が設定される理由
そもそもなぜ営業には目標が設定されるのかについて考えてみましょう。
- 会社が存続していくため
- 会社が営業を評価しやすくなる
- 営業のモチベーションを上げるため
理由1:会社が存続していくため
会社を経営していくためには、必要な売上や利益を確保していかなければなりません。
そのために会社全体としての売上や利益目標を設定していくのですが、このままでは誰がどのくらい頑張ればいいのか分かりませんよね。
そこで、部署単位や個人単位に売上目標を割り振っていくことになるのです。
理由2:会社が営業を評価しやすくなる
何も基準がないままだと、結果が出てもそれが良いのか悪いのか評価しづらいです。
しかし、明確な目標数値(=基準)があることによって、目標を達成した営業の評価は高くなり、目標を下回った営業の評価は低くなるといったように、会社が営業を評価しやすくなります。
理由3:営業のモチベーションを上げるため
人は何かの目標があることで、それに向かって努力することができます。
そして、その努力をした結果、報酬を得たり、スキルが身についたりして、さらに仕事の楽しさにハマっていくなんてこともあります。



逆に目指すものがないと、営業のパフォーマンスが落ち、会社全体のパフォーマンスが落ちてしまいます。
営業が目標達成するための考え方
先ほどもお伝えしましたが、目標を達成するための基本的な考え方は「見込み顧客管理(=パイプラインマネジメント)」です。
時間には限りがあるので、営業はいくつかの案件をこなしながら、なるべく優先度の高い案件に注力して受注していきたいと思いますよね?
しかし、その営業活動の中で、見込みが低いと感じた案件に見切りをつけたりもしますが、一方で、見込みが高いと思っていた案件が失注してしまったりということも発生してしまいます。
なので、ある一定の成果を出していくには、目標から逆算して絶えず「案件」を仕込んでおく必要があります。これが見込み顧客管理の考え方です。


この見込み顧客管理の考え方を持っていないと、1件受注ができると、次に受注の可能性が高い案件だけに注力をしてしまって、仮にそれが失注してしまうとしばらくの間、受注できそうな案件がなくなってしまうといった事態に陥ってしまいます。
そのため、ある程度失注してしまうことも見越しながら、複数の案件をパイプラインの中に投入していかなければなりません。



これが、安定的に目標を達成できるかできないかのポイントになります。
営業が目標達成するためのステップ
先ほどの見込み顧客管理をするための具体的なステップについて解説します。
- 案件の商談ステータスと確度の洗い出し
- 確度から案件の見込み額を算出
- 具体的な行動量(=パワー配分)を決める
ステップ1:案件の商談ステータスと受注確度の洗い出し
まずは、今抱えている案件毎の商談ステータスと受注確度を洗い出していきます。
商談ステータスについては、アプローチ前、情報収集、プレゼン、クロージング等と通常の営業フローに合わせて設定していきましょう。
アプローチ前や情報収集ステータスにおいては、不確実性がかなり高いので受注確度は低めであるCランク(30%)やDランク(10%)にします。
プレゼンステータスは、ある程度自社が有利なのか不利なのか判断がついている場合がありますが、依然として読み切れないのでAランク(80%)はつけず、Cランク(30%)やBランク(50%)にします。
クロージングステータスは、契約書などの事務手続きだけということであればAランク(80%)、プレゼン内容の修正が必要であればBランク(50%)にしておきましょう。
この受注確度をどうするかについては、これまでの経験値を参考にしながら、「ニーズを引き出せたらCランク」「キーパーソンに直接プレゼンできたらBランク」といったように具体的な行動を基準に決めていきます。
ステップ2:案件の受注確度と金額から見込み額を算出
次に、案件毎の受注確度と金額の掛け算から商談ステータス毎の見込み額を算出していきます。
たとえば、以下のようになっている場合、クロージングステータス(約2週間以内)においては、1,300万円(=1,000万円×80%+1,000万円×50%)が見込めるといった具合です。
一方で、情報収集ステータスを見てみると、このまま営業活動を進めていくと1~2か月後の受注金額は380万円しかないということが可視化できます。
このように管理をしていると、各案件の受注確度を上げるための行動をしなければならないのか、ステータス毎の案件を増やす行動をしなければならないのか明確になります。


ステップ3:具体的な行動量(=パワー配分)を決める
たとえば、A~Jまでの商談があり、仮に全て100万円規模の案件として、A~Eまでの受注確度は10%、F~Hまでの受注確度は50%、IとJの受注確度は80%とします。
仮に、どの案件にも均等に注力してしまった場合、A~Eへはパワーを50%、F~Hへはパワーを30%、I~Jへはパワーを20%を割いてしまい、期待金額は100万円×{10%×5(A~E)+50%×3(F~H)+80%×2(I~J)}=360万円となってしまいます。
しかし、限られた時間の中で、最大のアウトプットを出す場合、見込みが低いものと見込みが高いものに同じパワーをかけるのはおかしいですよね。


仮に、A~Eへ注いでいた50%のパワーのうち、20%をF~Hに投入して受注確度を80%に上げて、20%を新規案件に注力し、その結果A~Eの受注確度は5%に下がるとしましょう。
そうなると、期待金額は100万円×{5%×5(A~E)+80%×5(F~J)}=425万円と、均等にパワーを割いていたときよりも期待金額は上がり、かつ、新規案件の開拓までできてしまいます。



このようにして見ると、行動量(=パワー配分)を決める重要性がわかりますよね。
まとめ
本記事では、営業が目標達成するための基本的な考え方や具体的なステップについて紹介しました。



営業のコツをまとめて知りたい方は、是非以下の記事もお読みください。