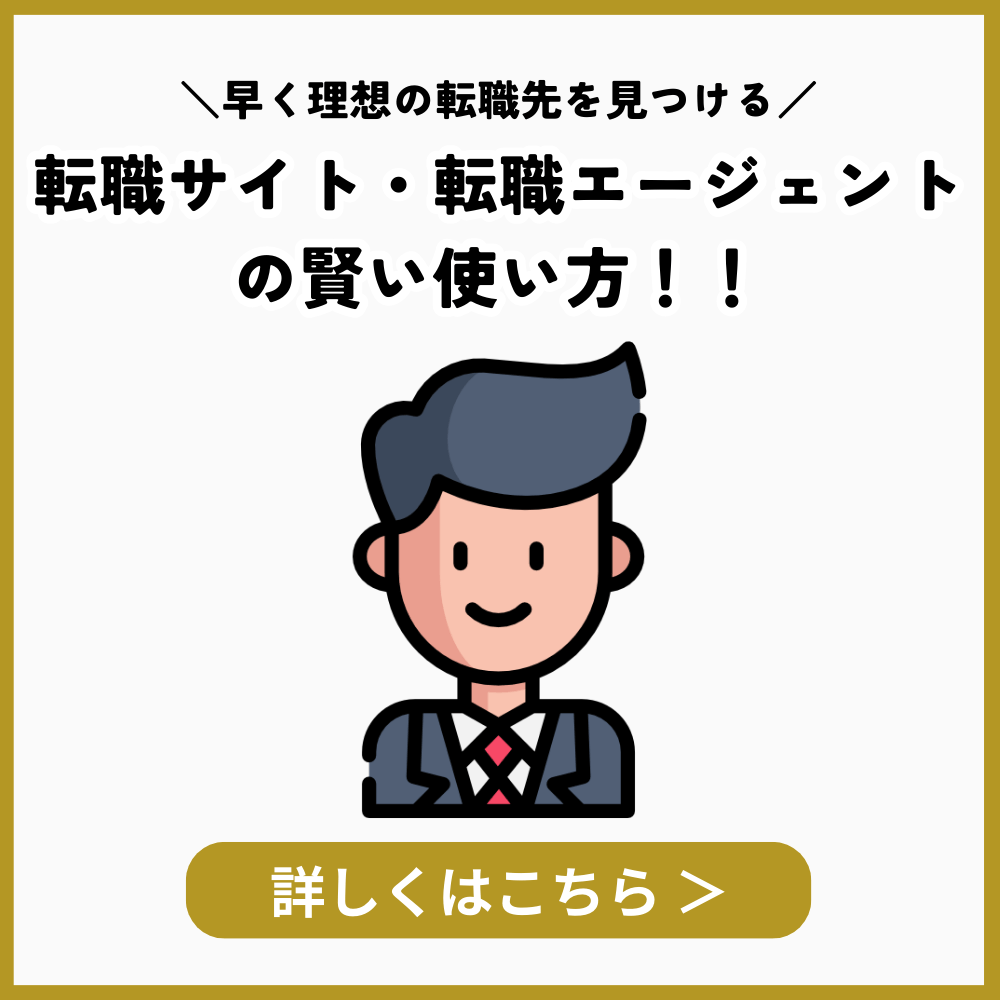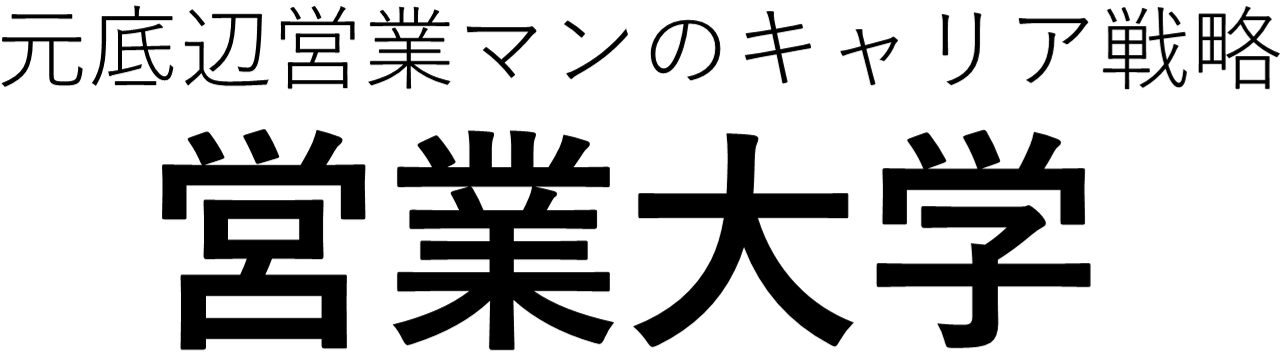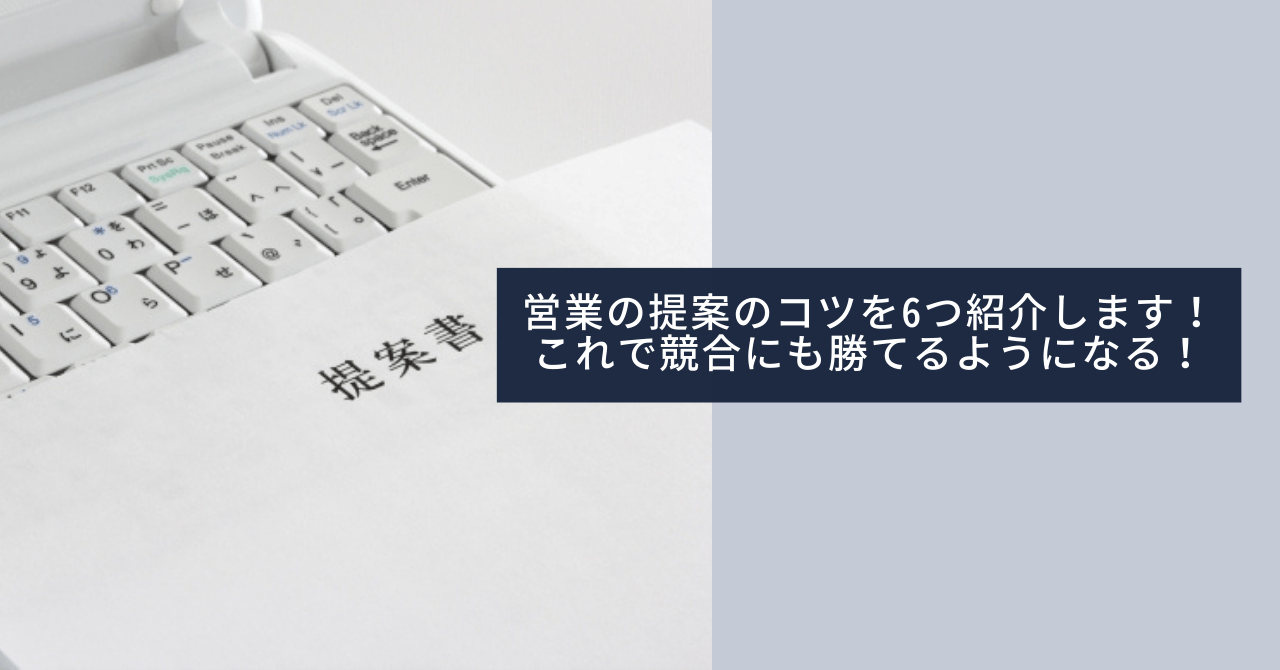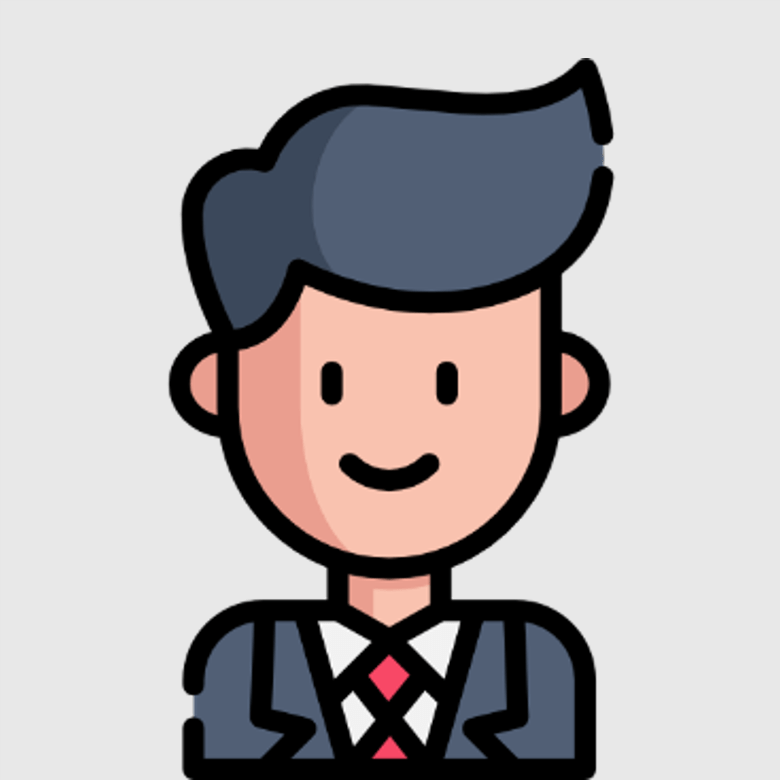- コンペに勝つためにはどうすればいい?
- 的を得た提案をしたい!
- 提案書にはどんな内容を盛り込めばいい?
このような悩みを解決する記事となっています。
顧客の課題を把握したらすぐに提案をしてませんか?
顧客の課題の解決策の方向性が合意できてない状態で提案をしたとしても、全く検討違いなもの提示してしまって「それはちょっと違う」と言われ、競合に負けて、提案書を書いた時間が無駄になってしまいます。
しかし、商談の序盤に解決策の方向性や範囲を決める「仮提案」をしておけば、そのような事態が避けられます。
ここでは、営業が仮提案をする重要性や実際のやり方・コツについてご紹介します。
営業における仮提案とは?
営業の種類に関わらず、営業の基本的なプロセスは以下のようになります。
- リスト選定
- ニーズの仮説構築
- アプローチ
- 面談(雑談/ヒアリング/仮提案)
- プレゼン・クロージング
- 見込み顧客管理
この営業のプロセスを見て頂くと、顧客に対していきなり「当社の〇〇という商品はおすすめです!」と提案するのは違うことが分かりますね。
リスト選定によって、買ってくれそうな顧客を選定して、ニーズの仮説構築によって、どのようなニーズを抱えてそうかあたりをつけ、顧客へのアプローチをして、面談をして、初めてプレゼン(提案)をしなければなりません。
また、実際に提案をする前に、仮提案をすることが重要で、仮提案が上手くいけば80%程度は契約できたも同然の状態まで持っていけます。
営業の仮提案の重要性
まず、そもそも「仮提案」とは、問題に対する解決策の方向性を示すものです。
それでは、具体的に仮提案をする重要性を3つ紹介します。
- 的外れな提案を避ける
- 解決策の方針に関わることができる
- 顧客側で取り組む価値を判断できる
重要性1:的外れな提案を避ける
問題が複雑であればあるほど、解決のための方法はいろいろな方法が考えられます。
たとえば、営業部の成績が悪い原因が「若手のスキルが低い」ということがわかったとした場合、外部の営業コンサルと同行する、外部の営業研修を受講させる、OJTを実施するといったいくつかの方法が考えられると思います。
このような状態でいきなり「営業研修のカリキュラム」の細かい提案をしたとしても、もし顧客側で「外部の営業コンサルに指導してもらう」といった解決策で検討していた場合は、全く的外れな提案になってしまいます。
なので、提案をする前に仮提案をすることによって、解決策の方針やその価値についての認識を合わせなければいけません。
重要性2:解決策の方針に関わることができる
逆に、まだ外部の営業コンサルに指導してもらう、外部の営業研修を受講させる、OJTを実施するといった解決の方針が決まってないのであればチャンスです。
解決の方針が決まってないのであれば、商談の早い段階から仮提案をすることによって、自社の強みが営業研修であるならば、自社の得意な領域に引き込むことも可能になります。
重要性3:顧客側で取り組む価値を判断できる
仮提案をすることは、営業側にメリットがあるだけでなく、顧客側にもメリットがあります。
顧客側である問題を解決しようとした場合に、時間、労力、お金をかけてまで取り組む価値があるのかどうかを判断する材料になります。
いくつかの解決策のアイデアがもらえるのと同時に、それぞれの解決策のメリット、デメリットを整理することができます。
もちろん、営業側にとっても、このように顧客に寄り添ってあげることによって、「あの営業マンと繋がっておくと当社にもメリットがありそうだ」となり、今後の展開を有利に運べる可能性も高まります。
営業の仮提案のコツ
解決策の方針やその価値についての認識が合ってない状態のままでは、顧客側もこちら側が提案しようとしている解決策がよいのかどうか判断ができません。
そのため、今後提案しようとしている解決策が、どんな課題を解決しようとしているものなのか、それが解決されることによってどのような利益をもたらすのか、他の解決策と何が違うのかといったものを事前に握っておかなければなりません。
これが仮提案です。仮提案をするときには以下の6つコツがあります。
- RFPが出る前に仮提案をする
- 解決策の方針と範囲を示す
- 顧客の戦略との関係性を示す
- 他の解決策との差別化を示す
- 解決策ともたらされる収益との関係性を示す
- 相手によって伝え方を変える
コツ1:RFPが出る前に仮提案をする
顧客の方から「このような解決方針に対する提案を出してくれ」といった提案依頼書(RFP)が出され、複数業者に競わせる場合があります。
このRFPが出てくると提案する側にとっては、解決策の方針と範囲が最初から決められているので、提案をしやすくなります。
しかし、一方でRFPに書かれている解決方針が必ずしも自社の得意領域になっているとも限らないのと、そもそもその解決方針が正しいものであるとも限りません。
なので、RFPに沿って提案をすると、競合に負けてしまう可能性があるのと、仮に競合に勝ったとしても、そもそもの解決方針が正しくなければ収益にもあまり貢献できず、「御社に任せたのが間違いだった」となり兼ねません。
したがって、RFPが出る前に仮提案を出さなければなりません。
 元底辺営業マン
元底辺営業マンそうすると自社の有利な方向に誘導できるのと、解決方針を正しい方向に誘導できるようになります。
コツ2:解決策の方針と範囲を示す
どのような課題に対して、どのように解決しようとしているのかを明らかにして、解決の方向性と範囲を決めていきます。
先ほどの例でいうと、外部の営業コンサルと同行する、外部の営業研修を受講させる、OJTを実施するといった解決策のうち、どの方法で解決していくのかを示していくことになります。
また、営業研修という解決策の場合は、何日間で実施するのか、研修後のアフターフォローまで含めるのかといった範囲を摺合わせていきます。



この時点では、営業研修の具体的なカリキュラム(解決策)までは必要ありません。
コツ3:顧客の戦略との関係性を示す
たとえ同じ課題であっても、顧客によっては採用する戦略が全く異なる場合があります。
たとえば、売上が低迷しているといった場合、商品の価格を変えないのであれば、新規顧客を上げるのか、既存顧客の購入単価を上げるのか/リピート率を上げるのか、といったいくつかの戦略が考えられますよね。
顧客が「新規顧客は順調に増やしてきているので、既存顧客の単価、リピート率をいかに増やすかに重点を置いている」と言うのであれば、新規顧客を増やすための広告をどうするかといった提案ではなく、既存顧客を増やすための解決策の話をしなければなりません。
コツ4:他の解決策との差別化を示す
提案しようとしている解決策が他の解決策とどう違うのか、どんなところにメリットがあるのか、どんなところにデメリットがあるのを伝えていくことになります。
「なんでデメリットまで伝える必要があるの?」と思うかもしれませんが、これは顧客からの信頼を得るために必要です。
「この商品はこれもあれも良いですよ」と良いところだけ言われると「でもデメリットもあるんでしょ?良いところばかり言いやがって」となりますが、「この商品は〇〇といったメリットがあるんですが、△△というデメリットもあるので、検討の際にはよくお考えください」と言われたほうが信頼できますよね?



しかし、単純にデメリットだけ言うと、そこが顧客にとって重要な要素だった場合、不利になってしまうので、もしデメリットをカバーできる余地があれば、「△△といったデメリットもありますが、◇◇のオプションを追加するとカバーできます」といったように伝えるようにしましょう。
コツ5:解決策ともたらされる収益との関係性を示す
解決策によって、業務プロセスがどのように改善され、それがどう市場から評価されて、収益の拡大に繋がるのかを明らかにしていきます。
収益の拡大に繋がるのは大きく2つの方向性があります。


一つ目は、顧客の商品やサービスそのものが改善されて、市場から評価されて、結果として収益の拡大に繋がるパターンです。
二つ目は、商品やサービスを提供するプロセスそのものを改善することで、コスト削減や生産性の向上によって収益の拡大に繋がるパターンです。
この2つを常に意識しながら「当社のサービスを導入することで、コストが〇円削減できます」といったように数字で明確に言えれば、解決策の価値は大きくなります。
コツ6:相手によって伝え方を変える
仮提案は、提示する人によって伝え方を変えなければなりません。
たとえば、上の人であればあるほど、その解決策によってどれくらい収益が見込めるのかといった経営課題に興味がありますが、現場の人であれば、その解決策によってどれくらい業務が楽になるのかといったような業務課題に興味があります。
なので、対面している人が何に興味がある人なのかを見極めて、その人の興味があるところを強調しながら伝えていかなければいけません。
まとめ
本記事では、営業が仮提案をする重要性や実際のやり方・コツについて紹介しました。



営業のコツをまとめて知りたい方は、是非以下の記事もお読みください。